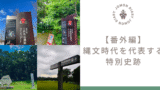環状列石(ストーンサークル)とは?
環状列石(ストーンサークル)とは、石を環状に並べたものです。縄文時代の前期頃から作られ始め、北海道・東北〜中部地方などで多く見つかっています。
環状列石の大きさや色はさまざまで、直径数十メートルの大規模なものや、数百~数千個の石で作られたものもあります。
「配石遺構」とは、石を一定の形に並べた遺構のことで、大規模な配石遺構は「環状列石」と呼ばれることが多いです。特に縄文時代後期に大きな環状列石が多く作られました。
用途ははっきりしていませんが、祭祀や集会の場、墓地、あるいは太陽や月の運行を示す暦の役割などがあったと考えられています。
暦としての役割を想像させる理由のひとつに、秋田県の大湯環状列石があります。野中堂環状列石の中心と万座環状列石の中心、さらにそれぞれの日時計状組石を結んだ線が、夏至の日の入り方向と一致しているのです。

日本の代表的な環状列石
まずは代表的な環状列石の規模や特徴を一覧で比べてみましょう!

東北地方には大規模な環状列石が多く、2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」に含まれるものもあります。
それでは詳細に各遺跡を見ていきましょう。
小牧野遺跡(青森県青森市)
青森県青森市の小牧野遺跡は縄文時代後期(約4,000年前)の遺跡で、大規模な環状列石で有名です。3〜4重に列石されており、直径55mと日本最大級の大きさです。
小牧野遺跡は約2,900個の巨大な石で作られており、9割が安山岩、残り1割が石英安山岩で構成されています。
石を縦横交互に並べる独特な配置は、「小牧野式配列」と呼ばれています。

伊勢堂岱遺跡(秋田県北秋田市)
秋田県北秋田市の伊勢堂岱遺跡は、縄文時代後期(約4,000年前)の遺跡です。
この遺跡は、まとまって4つの大きな環状列石が見つかっているのが特徴的で、そのどれもが直径30m以上と非常に大きいです。
周辺の小猿部川などから集められたおよそ4,000個もの石が使われています。
しかも、20種類を超えるカラフルな石が用いられているとのことで、訪れる際には、それぞれの石の色の違いにも注目すると面白いでしょう。

大湯環状列石(秋田県鹿角市)
秋田県鹿角市の大湯環状列石は、縄文時代後期(約4,000年前)の遺跡です。「万座」と「野中堂」という2つの巨大なストーンサークルから構成されています。
万座環状列石では約6,500個の石が使われていて、特に「石英閃緑玢岩」という緑色の石が6割を占めているのが特徴です。同じ秋田県の伊勢堂岱遺跡はカラフルな石を用いており、大湯環状列石と見比べると、それぞれの個性ある石使いの違いを楽しめます。
大湯環状列石と伊勢堂岱遺跡は車で約1時間の距離にあるため、レンタカーを利用すれば1日で両方を訪れることができます。

御所野遺跡(岩手県一戸町)
御所野遺跡は、岩手県一戸町に位置する縄文時代中期後半(約5,000〜4,200年前)の遺跡です。
御所野遺跡は配石遺構が多く見つかっています。使われた石の中には、茂谷山から運んできた花崗岩も含まれています。
配石遺構の周辺では墓穴が見つかっており、御所野遺跡の広いむらの中で配石遺構周辺は墓地として使われていたと考えられています。

湯舟沢環状列石(岩手県滝沢市)
岩手県滝沢市の湯舟沢環状列石は、縄文時代後期(約4,000年前)の遺跡です。
900個ほどの大小さまざまな石で構成されていて、安山岩が使用されています。
全体を俯瞰すると円形に見えますが、個々の石は直線や四角形に配置されるなど複雑で独特な形をしています。調査によると、石組の下には人が埋葬されていたと思われる痕跡も見つかっています。

【番外編】木や海外の例
チカモリ遺跡(石川県金沢市)
番外編として、「石」ではなく「木」を使った環状遺構もあります。
石川県金沢市のチカモリ遺跡では、縄文時代後期から晩期(約3,000〜2,300年前)に、クリの木を円状に並べた大きな環状木柱列(ウッドサークル)が作られていました。10本の柱が円を形成し、さらに2本は門のような役割を持つ配置になっていたことが確認されています。

ストーンヘンジ(イギリス)
また、海外の例としてイギリスのストーンヘンジがあります。
約5,000年前から建造が始まり、遠方から運んだ巨大な石を立てて並べた遺構で、お墓が確認されていることから儀礼用の神殿として使われたとも考えられていますが、多くは謎に包まれています。
ストーンヘンジも太陽の動きと石の配置に関係があるとされ、日本の環状列石と似た特徴を持っています。
まとめ
- 環状列石は縄文時代に作られた石の環状遺構で、祭祀・集会・暦などさまざまな役割が考えらている
- 東北地方に大規模なものが多く、小牧野遺跡や大湯環状列石などは特に有名
- 石の種類や配置の工夫から、縄文人の高度な技術や天文知識がうかがえる
- 同時期には、日本国内での木を使った例や海外のストーンヘンジなども作られており、世界各地で環状の遺構が重要な意味を持っていたことがわかる
縄文についてさらに知る
記事内に広告(PR)を含む場合があります。